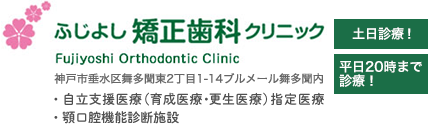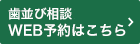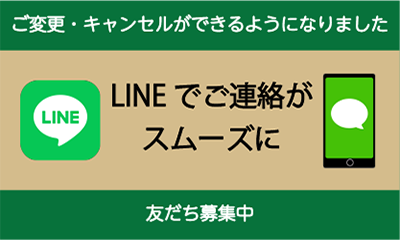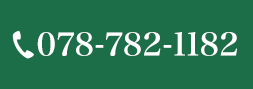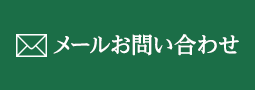叢生(ガタガタの歯ならび)の治療例
症例1


| 主訴 | 歯がガタガタ |
|---|---|
| 診断名あるいは主な症状 | 叢生 |
| 年齢 | 12 歳 |
| 治療に用いた装置 | Wタイプ拡大装置、マルチブラケット装置 |
| 抜歯部位 | 上下両側第1小臼歯 |
| 治療期間 | 1期治療 2 年、2期治療 1 年 6ヶ月 |
| 治療費 | 957,000円(税込) |
| リスク副作用 | ・不十分な歯磨きにより虫歯や歯周病になることがあります。また食事の内容や摂り方も原因になります。 ・治療全般にわたって装置の使用方法・使用時間が守れない場合は、治療期間の遅延や治療結果に悪い影響を及ぼすことや予想外のトラブルが発生することがあります。 ・理由に関わらず来院しないことや遅刻が重なる場合、予定以上に治療期間の遅延や治療結果に悪い影響が生じることがあります。 ・成長期、特に思春期成長時に顎顔面の過成長がみられ、重度の骨格性不正咬合を呈した場合は矯正治療単独では限界があるため、第2期治療に移行できないことがあります。 |
解説
前歯のガタガタを気にして受診されました。平均的な日本人より小顔にもかかわらず、歯の幅が著しく大きかったため、上下歯列拡大ののち、小臼歯を抜歯してマルチブラケット装置で治療しました。
※治療に用いた装置や治療方法は一例であり、全ての症例に当てはまるわけではありません。
出っ歯(上顎前突)の治療例
症例2


| 主訴 | 口が閉じられない |
|---|---|
| 診断名あるいは主な症状 | 上顎前突 |
| 年齢 | 11歳 |
| 治療に用いた装置 | 機能的矯正装置、マルチブラケット装置 |
| 抜歯部位 | 抜歯せず |
| 治療期間 | 1期治療 2 年、2期治療 2 年 |
| 治療費 | 957,000円(税込) |
| リスク副作用 | ・不十分な歯磨きにより虫歯や歯周病になることがあります。また食事の内容や摂り方も原因になります。 ・治療全般にわたって装置の使用方法・使用時間が守れない場合は、治療期間の遅延や治療結果に悪い影響を及ぼすことや予想外のトラブルが発生することがあります。 ・理由に関わらず来院しないことや遅刻が重なる場合、予定以上に治療期間の遅延や治療結果に悪い影響が生じることがあります。 ・成長期、特に思春期成長時に顎顔面の過成長がみられ、重度の骨格性不正咬合を呈した場合は矯正治療単独では限界があるため、第2期治療に移行できないことがあります。 |
解説
口を閉じても前歯が見えるほどの出っ歯でした。下顎の前方成長を促すため機能的装置を使った後、歯を抜くことなくマルチブラケット装置で治療しました。
※治療に用いた装置や治療方法は一例であり、全ての症例に当てはまるわけではありません。
受け口(反対咬合)の治療例
症例3


| 主訴 | 受け口 |
|---|---|
| 診断名あるいは主な症状 | 反対咬合 |
| 年齢 | 5 歳 |
| 治療に用いた装置 | 歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)、急速拡大装置、 拡大床矯正装置、機能的矯正装置 |
| 抜歯部位 | 抜歯せず |
| 治療期間 | 1期治療 7 年、2期治療 なし |
| 治療費 | 429,000円(税込) |
| リスク副作用 | ・不十分な歯磨きにより虫歯や歯周病になることがあります。また食事の内容や摂り方も原因になります。 ・治療全般にわたって装置の使用方法・使用時間が守れない場合は、治療期間の遅延や治療結果に悪い影響を及ぼすことや予想外のトラブルが発生することがあります。 ・理由に関わらず来院しないことや遅刻が重なる場合、予定以上に治療期間の遅延や治療結果に悪い影響が生じることがあります。 ・成長期、特に思春期成長時に顎顔面の過成長がみられ、重度の骨格性不正咬合を呈した場合は矯正治療単独では限界があるため、第2期治療に移行できないことがあります。 |
解説
受け口を気にして受診されました。前歯が永久歯に生え代わっても上の歯が前に出る可能性が低いと判断し、まずは歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)で受け口を治療しました。前歯が永久歯に生え代わると凸凹が目立つようになったので上顎急速拡大装置と下顎可撤式床拡大装置で歯列を拡大しました。その後、機能的矯正装置で上下の顎と歯の位置を整えたところ、マルチブラケット装置による2期治療は不要となりました。
※治療に用いた装置や治療方法は一例であり、全ての症例に当てはまるわけではありません。
開咬(オープンバイト)の治療例
症例4


| 主訴 | 前歯で咬み切れない |
|---|---|
| 診断名あるいは主な症状 | 開咬 |
| 年齢 | 28 歳 |
| 治療に用いた装置 | 歯科矯正用アンカースクリュー、マルチブラケット装置 |
| 抜歯部位 | 下顎両側第1大臼歯 |
| 治療期間 | 4年 |
| 治療費 | 957,000円 (税込) |
| リスク副作用 | ・不十分な歯磨きにより虫歯や歯周病になることがあります。また食事の内容や摂り方も原因になります。 ・治療全般にわたって装置の使用方法・使用時間が守れない場合は、治療期間の遅延や治療結果に悪い影響を及ぼすことや予想外のトラブルが発生することがあります。 ・理由に関わらず来院しないことや遅刻が重なる場合、予定以上に治療期間の遅延や治療結果に悪い影響が生じることがあります。 ・成長期、特に思春期成長時に顎顔面の過成長がみられ、重度の骨格性不正咬合を呈した場合は矯正治療単独では限界があるため、第2期治療に移行できないことがあります。 |
解説
上下の歯が、奥歯でしか当たらない状態でした。 下顎の第1大臼歯が根っこの治療を受け、金属の差し歯をかぶせていたため、 健康な第3大臼歯(親知らず)を代わりに活かして治療しました。上顎にプレート型、下顎にネジ型の歯科矯正用アンカースクリューとマルチブラケット装置を使用しました。
※治療に用いた装置や治療方法は一例であり、全ての症例に当てはまるわけではありません。
過蓋咬合の治療例
症例5


| 主訴 | 上の前歯がでている |
|---|---|
| 診断名あるいは主な症状 | 過蓋咬合 |
| 年齢 | 10 歳 |
| 治療に用いた装置 | 咬合斜面板、マルチブラケット装置 |
| 抜歯部位 | 抜歯せず |
| 治療期間 | 1期治療 3 年、2期治療 1年 3 か月 |
| 治療費 | 957,000円(税込) |
| リスク副作用 | ・不十分な歯磨きにより虫歯や歯周病になることがあります。また食事の内容や摂り方も原因になります。 ・治療全般にわたって装置の使用方法・使用時間が守れない場合は、治療期間の遅延や治療結果に悪い影響を及ぼすことや予想外のトラブルが発生することがあります。 ・理由に関わらず来院しないことや遅刻が重なる場合、予定以上に治療期間の遅延や治療結果に悪い影響が生じることがあります。 ・成長期、特に思春期成長時に顎顔面の過成長がみられ、重度の骨格性不正咬合を呈した場合は矯正治療単独では限界があるため、第2期治療に移行できないことがあります。 |
解説
上の前歯が下の前歯を深く覆っている状態でした。1期治療で咬合斜面板でかみ合わせを浅くすると同時に、下顎の前方成長を促しました。2期治療では歯を抜くことなくマルチブラケット装置で治療しました。
※治療に用いた装置や治療方法は一例であり、全ての症例に当てはまるわけではありません。
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
(日本矯正歯科学会ホームページより抜粋)
矯正治療には以下の一般的なリスク・副作用があることをご理解ください。
※すべてのリスクや副作用が生じるわけではありません。
・歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。
・装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。
・ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
・治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。
・歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
・装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。
・あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。
・治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えてい る骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。