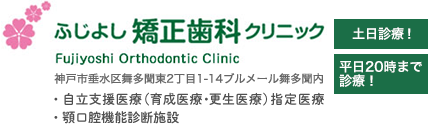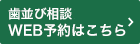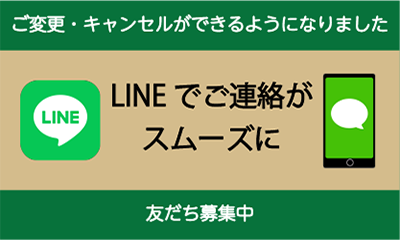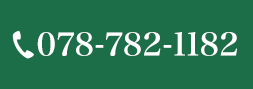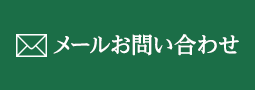インフルエンザとお口の中の環境は関係ある?ない?

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
今回は、ここ最近ずっと猛威を振るっている「インフルエンザ」についてお話をしていきます。
皆さん、ご存じでは無いかもしれませんが、インフルエンザとお口の中の環境(健康)は、とても関係があります。それはなぜ?と思いませんか?良かったら最後まで読んでくださると嬉しいです。
今季のインフルエンザは例年とは違います!

毎年、冬の始まりとともに12月頃~2月頃になるとインフルエンザが大流行します。コロナが流行した年は、皆さんがウィルスの感染予防に徹底して行っていたため、インフルエンザが流行することがありませんでした。
しかし、コロナも落ち着き2023年5月8日にインフルエンザと同様の「5類感染症」となりました。そうすると感染対策もゆるくなり、街の中や・電車の中でもマスクをつけていない方々が増えたことを思い出してみてください。
そしてその年の冬からまたインフルエンザが流行ってしまいました。それでも去年までは、流行るころには学級閉鎖や学年閉鎖になることはありましたが、今年はどうやら学校閉鎖にもなってきていることに驚いています。
当院でも、毎日のようにインフルエンザによる予約のキャンセルのお電話があります。今季、流行っているインフルエンザは例年と違い、インフルエンザA型の変異した「サブグレートK」という変異株が子供の世代で流行っているそうです。この変異株は、今までにインフルエンザに罹患し、免疫がある方や・インフルエンザの予防接種をしていても感染してしまうことです。
普通に風邪をひいてしまうだけでも体はつらいのに、インフルエンザは高熱や関節など体の節々が痛くなり寝込んでしまうことも多く脳炎や肺炎など重症化してしまうことも多いです。
インフルエンザはどう感染するのか?

インフルエンザは、インフルエンザウィルスの感染です。ウィルスは、通常、人の体の中には存在していません。外部から人の体の中に入り込んで、体の中の細胞をとりこみながら急速に増加していきます。この、外部というのは「目」・「鼻」・「口」です。
インフルエンザウィルスが増加することで、人は「異物」と認識するため、急速に増加した異物を倒そうとします。体がインフルエンザウィルスという異物と戦っているときに、高熱やのどの痛み・関節の痛みなどにあらわれます。
目からの感染(結膜)
ウィルスの感染は、目からもします。石鹸で手を洗わずに、いろいろ触れた手で目をこすってしまうと、手について見えないウィルスが目の結膜につき、感染します。しっかりマスクをしていても、石鹸で洗っていない手で目を触ると意味がなくなりますのでできるだけ目を触らないようにしましょう。
-
コンタクトレンズをお使いの方ならご存じでしょうが、コンタクトレンズを目に入れる前には必ず石鹸で手を洗ってからと指導されているはずです。同様に、目を触るときは必ず石鹸で手を洗うよう普段からの習慣にするようにしてください。
鼻・口・からの感染(上気道)
ウィルス感染で一番多いのが、この鼻と口からではないでしょうか。
ウィルスに感染している方が咳やくしゃみをするとウィルスを含んだ飛沫がとびます。この飛沫を吸い込んでしまい飛沫感染をしてしまいます。しっかりマスクをしていないと街中ですれ違っただけでも感染する可能性があります。
飛沫を吸い込むことの他にも、目(結膜)と同じようにウィルスがついた手で鼻やお口を触ってしまうことで感染します。マスクをしていても、マスクの表面にはウィルスが付着しているので、マスクを外すときにも表面を触らないように外し捨てましょう。
お口の中にいる細菌がウィルスの感染を助けてしまう

皆さんのお口の中には、沢山の種類の細菌がいます。もちろんお口の中の健康を保ってくれる良い細菌もありますが、舌が白くなってしまい口臭の元になる細菌や虫歯になってしまう細菌もあるなかで一番悪さをおこすのが歯周病菌です。
成人した方のお口の中にはほぼ全てのかたのお口の中には歯周病菌がいます。年齢を重ねていく加齢や、歯磨きが不十分でお口の中の環境が悪いと歯周病が悪化し、歯周病菌が増えてしまいます。
この歯周病菌が実はインフルエンザの感染の率が上がることも研究でわかっています。歯周病は、歯が抜けてしまう病気ですが、歯が抜けるだけではなく全身の疾患にも影響します。そのうえ、インフルエンザにもかかりやすくなってしまうなんて・・・。歯周病を放置せず、かかりつけの歯科医院に定期的に通い歯周病が悪化しないように気を付けてください。
インフルエンザの予防には「手洗い・うがい・マスク」さらに口腔ケア

インフルエンザはワクチン接種だけではなく、風邪の予防でもですが基本的に「手洗い」・「うがい」・「マスクの着用」が大切です。
この三つにあわせてお口の中を綺麗に保つこともインフルエンザの予防にはとても重要です。正しい歯磨きは出来ていますか?歯ブラシで丁寧(歯間ブラシやフロスも使う)に歯磨きをし、お口の中が乾燥しないよう常に鼻呼吸を意識しておこないましょう。
普段から口での呼吸が習慣していると唾液の量が減ってしまうと悪い細菌を洗い流すことができません。唾液が減らないよう、食べるときは良く噛むなども意識してみましょう。
まとめ

今回は、学校閉鎖までになっているインフルエンザとお口の中の環境・お口の中を清潔に保つお話をしました。
インフルエンザにかぎらず、風邪などでも体調が悪く寝込んでしまうと、ついお口の中のケアは忘れ気味になってしまいます。
普段の生活から、正しい歯磨きが出来ていればウィルスの感染も防ぐことができます。正しい歯磨きが出来ているか、かかりつけの歯科医院を受診してみてください。
「手洗い・うがい・マスク・お口の中にケア」忘れずにしてインフルエンザにならないようお気をつけください。
当院では、Instagramもやっております。ぜひ、そちらもご覧ください。
良質な睡眠にはお口の中の環境が大切②

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
前回は、良質な睡眠とは何か?良質な睡眠は、人が生きることにとても必要なことについてお話しましたが、今回は、良質(質が良い)な睡眠どころか毎日睡眠不足だと人の体やお口の中や歯にどんな悪い影響がでてしまうのかをお話していこうかと思います。
人の三大欲求の一つでもある「睡眠」ですが、眠る時間が少なかったりして寝不足が続いていたり、逆に寝すぎて睡眠時間が多すぎたりしてしまうことは(寝すぎ)、脳や体や心の不調だけではなく、お口の中や歯にも悪い影響が出やすくなります。歯とお口の中を健康に保つことは良い睡眠にもつながります。
睡眠の質が悪い(寝不足)ことがお口の中の環境に悪い理由

日常の生活が忙しくなると眠る時間が少なくなり、どうしても睡眠不足になりがちです。眠る時間もですが、睡眠の質が下がってしまうといつもと同じ時間寝ていたとしても体の疲れが取れなくなり、眠気が日中の生活をしているときにもでてくるようになります。日中に眠気が残っていると勉強や仕事での集中力も落ちますし、物事を楽しむ・美味しいものを食べるなどの楽しむ意欲も落ちてしまいます。
そして集中力や意欲が落ちるとともに、体の免疫力も低下してしまうのです。免疫力が下がってしまうと人は体調を崩しやすくなり風邪をひいてしまったり口内炎ができたり歯周病が悪化するようになります。また、眠っているときは、食事をすることも水などの水分補給もできないため唾液の分泌が起きているときよりも減ってしまいます。
・唾液の量が減ってしまう
・唾液が減ることで口臭がきつくなってしまう
・体の免疫力が下がってしまう
・歯周病が悪化してしまう
・虫歯の進行が早くなる
寝ているときにおこる歯に悪いこと
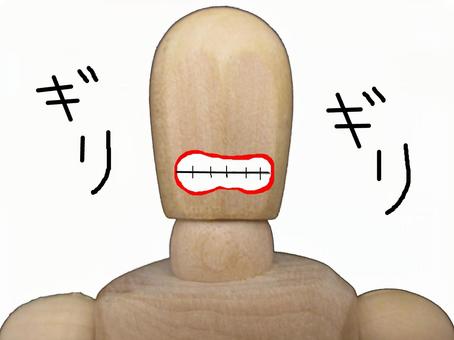
人は、眠りにつくと体が弛緩(しかん)して全身の筋肉の緊張がなくなります。緊張をなくすことで、その日の体の疲れやストレスを緩和しようとし体と心のバランスを整えます。しかし、日中に強いストレスを感じたりしてしまうと、寝ているときにその強く感じたストレスを体が元に戻そうと頑張るとそれが歯ぎしりや食いしばりといった歯やお口の中の健康を害することがおこります。
・歯ぎしり
・食いしばり
・歯周病や虫歯の悪化
・口呼吸
・ドライマウス
・睡眠時無呼吸症候群
-
歯の本数と睡眠は実は大きな関係があります

「8020」この数字、テレビのCMなどでも耳にすることがありませんか?
これは、80才まで20本の歯を健康に残そうという8020運動です。永久歯は全部で28本あります。(親知らず4本あるかたは32本になります)この28本の永久歯をずっと維持していくのは実は大変で、年齢が高齢になるとどうしても歯は歯周病や疾病によって抜けてしまい永久歯の本数が少なくなっていきます。
では、永久歯が残っている本数と睡眠がなぜ関係しているのか?それは、歯は食べ物も口に入れ歯で噛み切りすりつぶして食べ物を飲み込みやすくする役割をもっていますが、歯の本数が少なくなってしまうと上の歯と下の歯の嚙み合わせがわるくなります。しかし、将来どの歯が抜けてしまうか分からないですよね。もし抜けてしまう歯が1本だけならまだしも全部の永久歯が抜けてしまい総入れ歯になる可能性もあります。
おじいちゃんやおばあちゃんが入れ歯をとったお顔を見たことありませんか?顔がいつもよりクシャっとなって下顎がしゃくれているような見た目になっていると思います。これは、全部の永久歯が抜けてしまい歯を失ってしまうと、支えてくれていた歯がない下顎は上のほうへ顎が回転してしまうからです。そうすると舌の位置が喉の奥に落ちてしまうので気道が狭くなります。気道が狭くなると眠っているときの呼吸が浅くなってしまい良い睡眠がとれなくなってしまいます。
いくつになっても質の良い睡眠をとるためには、永久歯を健康な状態でお口の中に保ち抜けてしまうことのまいように、定期的に歯科医院に通って虫歯や歯周病のチェックと歯のクリーニングをおすすめします。何歳になっても自分の歯で噛んで食べることはとても大切で幸せなことです。
歯とお口の中を健康にし、より良い睡眠にするためにすること

乳歯や永久歯もしっかりとしたケア(歯磨き)をしないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなり、虫歯が進行してしまうと歯を削って治療します。歯は、一度虫歯治療のために削ってしまうと二度と元には戻りません。今は、セラミックやジルコニア、インプラントの技術も高くなりお口の中にはいっているかたも多いかもしれませんが、やはり乳歯が抜けて永久歯になり虫歯の治療をしていない天然歯が一番です!食べた時の感覚の食感や味覚も天然歯に勝るものはありません。お口の中は、歯だけではなく歯肉(歯茎)や唇や舌もあります。
ほっぺたの内側や唇に口内炎ができてしまって痛みで眠れなくなることもありますし、被せものがとれたまま歯科医院で治療せずに放置していると痛みがでて痛みで眠ることができなくなってしまいます。歯だけではなく、痛みを感じたまま良い睡眠をとることはできません。しかし、歯は定期的に歯科医院に通うことで虫歯・歯周病を早く見つけることもでき悪化することも防ぐことになります。
・眠る前の歯磨きは時間をかけ丁寧に磨くようにする
・歯ブラシ以外にも歯間ブラシやフロスを使うようにする
・歯磨きをしているのに虫歯や歯周病になりやすいと思ったら歯科医院で歯ブラシの当て方や磨き方を教えてもらう
・歯が痛い・歯茎から出血する・歯がしみると感じたらすぐに歯科医院を受診する
・歯が痛くなる前に定期的に歯科医院を受診し定期健診をするようにする
・寝ているときに歯ぎしりや食いしばりをしているようなら歯科医院に相談をする(マウスピースやナイトガードを作ってもらう)
まとめ

今回は、睡眠不足(寝不足)が歯と睡眠に関係していることや、人が眠っているときに実は歯やお口の中には悪いこと(悪影響)など、それを改善するためには毎日の丁寧な歯磨きや定期的に歯科医院に通う必要性についてお話してきました。
毎日、食べ物を噛んですりつぶしてくれる歯と毎日の睡眠はとても関係しています。「良質な睡眠」をとるために寝具やリカバリーウエアーを買って眠る環境を整えることを必要なことですが、ぜひお口の中にも気をつかっていただきたいです。
睡眠の質を今よりも向上されたいかたは、歯に痛みがなくても一度、お近くの歯科医院に行ってみてください。歯科医師はお口の中を診るだけで、歯ぎしりや食いしばりがあることがわかります。最近、歯科医院に行ってない方は一度ご相談してみてください。
当院では、Instagramもやっております。ぜひ、そちらもご覧ください。
良質な睡眠にはお口の中の環境が大切①

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
今回は、睡眠とお口の中の環境のかかわりについてお話していきます。
最近、「良質な睡眠」って言葉をよく目にしたり耳にしたりしませんか?
「良質=質の良い睡眠」ですが、質の良い睡眠とはどんな睡眠かご存知でしょうか?睡眠の質を高めるために、マットレスや枕を買い替えるなどしている方もおられますし、また最近では、寝ている間に体を回復するリカバリーウェアーなども人気ですよね。人間もですが、動物や虫や魚など含めても眠らない生き物はいません。生きることにとても重要なことは睡眠なのです。この大切な眠ること(睡眠)ですが、実はお口の中の環境と深く関係しています。
睡眠時間が少ない、または足りていないなどの睡眠不足が続いてしまうと、「唾液が減る」・「体の免疫力が落ちてしまう」など起りやすくなるため、虫歯や歯周病になるリスクが高くなりますし、唾液が減ることでドライマウスになり口臭の原因にもなります。体の免疫力が落ちる(低下する)と、口内炎ができ、細菌やウイルスへの抵抗が落ちてしまい、風邪やインフルエンザなどの感染症になりやすくなります。
皆さんの毎日の睡眠時間は何時間ですか?

みなさんの毎日の睡眠時間は何時間ぐらいですか?
ショートスリーパーという言葉がありますが、一日4~5時間ぐらいの睡眠でも体調が良いままの状態を保つことができる方もおられるようですが、年齢や性別・お仕事の内容にもよって睡眠時間は違うと思いますが、平均6~8時間が一般的な睡眠時間のようです。この時間は、健康な人の平均的な睡眠時間なので、風邪をひいていたりして、体調が悪いときなどは体が回復するのを助けるためにももっと長い時間の睡眠と休息が必要です。
いつもより睡眠の時間が短い寝不足の状態が何日か続いてしまうと、疲れがなかなかとれないなど体調が悪い状態になってしまいますが、睡眠の時間が足りていない寝不足はお口の中の環境や歯にも大きな影響があります。口内炎ができやすくなってしまい、虫歯や歯周病が前よりも進行してしまう原因になります。
良質(質の良い)な睡眠とはどんな睡眠?

最近、テレビやネット、SNSなどでもよく耳にすると思いますが「良質な睡眠」とは、どんな睡眠なのか、なにの質を良くすればいいのか分からないことはないでしょうか?
高級な寝具(マットレスや枕や布団)で寝ても自分にその寝具が合っていないと、朝起きた時に腰が痛くなる場合もあるので難しいですよね。値段が少しお高いホテルや旅館に泊まっても枕が合わず寝つきが悪くなってしまう経験もあると思います。
質の良い眠り(睡眠)とは、お布団に入ったら自然と眠気がおき、そのまます~っと眠りにはいることができ、夜中や起きる予定よりも数時間早く起きてしまうこともなく、朝までぐっすり眠ることができ、起きた時に前日の疲れを感じることなくスッキリと目覚められることです。「寝つきよく」「ぐっすり眠り」「すっきり起きる」この三つが合わさって良質な睡眠という良い眠りになります。
大切なのは睡眠の時間ではなく「質」

睡眠時間が長い=質の良い睡眠がとれていることではありません。逆効果になることがあります。例えば、休日などで特に予定が無い日などのときいつもの起きる時間より長く寝てしまった場合、起きた時に体が重く感じるようなことがありせんか?二度寝してしまった場合も同じです。例えば、いつもは登校や出勤のために朝6時ぐらいに起きているのに、お休みの日に朝10時まで寝てしまうと、「よく寝たからすっきりした」ではなく、「寝すぎてしんどい」ってなってしまいます。それは、なかなか目覚めることができず体がいつもよりも重く感じられ、いつもの睡眠時間よりも長く眠ってしまったことで同じ姿勢が続いてしまい、体の筋肉の血行が悪くなり腰や背中・首などが痛みを感じ、頭痛がするなどの症状がでます。
この症状は、寝すぎたことによって、いつもの睡眠のサイクルやリズムが崩れてしまい体内時計が狂ってしまっているからです。海外旅行に行った際に時差ぼけになるのと似た症状が寝すぎによってなるのです。睡眠にとって必要なのは、何時間寝た(眠れた)ではなく、朝目覚めたときにスッキリとして前日の体と心の疲労が取れているのが、良い(良質)睡眠になります。
もちろん体調が悪いときは、ゆっくりと休むことが一番大切です。休日で予定がないからと、いつもより長く寝てしまいお家から出る予定もないときなど、昼前ぐらいまで寝て起きて顔も洗わず歯も磨かず…なんて絶対にダメですよ!起きてすぐのお口のなかには細菌がいっぱいいます。虫歯や歯周病だけではなく口臭が酷くなる原因になります。休日であっても、体内時計が狂わないようにするために睡眠はいつもと同じ時間に眠りにつき、いつもと同じ時間に起きる習慣を心がけるようにしましょう。
睡眠障害とは?

睡眠障害というとあまり聞きなれないかもしれませんが、「不眠症」のことを睡眠障害といいます。不眠症はよく耳にすると思いますが、睡眠障害には大きく分けると三つの障害がありますが、一つだけ当てはまる方もいれば二つ以上当てはまる方もおられます。体は疲れているのに、寝ようとしてもなかなか眠れない・寝ている時に変な時間で起きてしまう・しっかりと寝たつもりなのに起きたときになぜか体がすっきりしない。など毎日でなくても一度や二度、誰もが経験しているのではないでしょうか?睡眠の障害が連日続くようであれば、専門の医師に相談していただき少しでも改善できるようになってください。
- ・なかなか眠れない(寝つきが悪い)【入眠困難】
- ・寝ているのに途中で目覚めてしまう【中途覚醒】
・起きようとした時間よりもかなり早くに目が覚める【早朝覚醒】
-
毎日、良質な睡眠をとるには

年齢や性別は関係なく、人は毎日生活しているだけで色々と疲れがたまりストレスを感じます。その疲れやストレスを翌日に持ち越さないためにも、毎日、しっかり眠ることが大切です。質のいい良質な睡眠をとるためには、眠るための環境や気を付けることがあります。寝室の気温や湿度も大切ですし、眠りに入る直前までスマートフォンやパソコンを見てしまうとブルーライトの光の刺激で脳が休まらず眠りの妨げになってしまいます。まずは、良質な睡眠をとれる環境づくりをしてみてください。
-
「眠る」という環境を整える
- ・お布団の中ではスマートフォンを見ない
・寝る前にタバコやカフェイン、アルコールなどの刺激物は控える - ・眠りにつく1時間~2時間前にゆっくり湯船につかる
- ・栄養のバランスがとれた食生活を心がけるようにする
- ・適度(1時間ほど)な運動を日中に行うようにする
- ・ストレスをためず解消できる方法や趣味を見つける
・起きる時間と寝る時間を崩さないようにする
-
まとめ

今回は、良質な睡眠についてお話しました。人の三大欲求の一つでもある睡眠は、健康に生きるためにとても必要で大切なことです。少しでもより良く質がいい睡眠をとっていくことが、身体の健康にも歯やお口の中の健康にも関係しています。次回は、睡眠の質が悪く寝不足な場合、お口の中や歯にどんな影響がでてしまうかお話していきます。
最後までコラムを読んでくださりありがとうございます。
当院では、Instagramもやっております。ぜひ、そちらもご覧ください。
右?左?どっちで噛んでいる?片噛み癖ありますか?

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
今回は、食べ物を噛むときの噛み癖についてお話していきます。
実は、先日、友人とご飯を食べていて対面にいる友人の口元の動きが気になりました。(職業病ですかね?つい口元や歯並びを見てしまいます笑)久しぶりに会った友人と二人で夕飯を食べに行ったのですが、食事の際に、食べる物を一口、口に入れたあと歯で噛んで食べ物をごくっと飲み込むまでの間、ずっと同じ歯だけで噛んでいました。ん?と思いしばらく会話そっちのけで口元を見ていたのですが、食べるときに前の歯を使わずに食べた物を口の中にいれたら同じ歯(友人は左側)でしか噛んでいないなぁ~。と気づいて本人に聞いてみたところ、「いつも左でしか噛んでいない。両方で噛むって何?」と真顔で言われびっくりしました!どうやら、前歯は上の歯と下の歯の間に隙間があり少し開咬気味で、右側の歯は上と下の奥歯の噛み合わせがあっていないようで、食べ物をかみ砕くことができないため、気が付いたら時から何十年もずっと噛める方の左側の奥の歯で食事をしているそうです。
皆さんはどうですか?
食べ物を食べる時は、全ての歯を使って食べることが基本です。前歯や犬歯をちゃんと使えていますか?おそらく無意識のうちに食べていると思いますが、友人のように、食事をする際、食べ物を噛む時に右側だけや左側だけなど、同じ方(片方)でばかり噛んでしまい食事をすることを「片噛み癖」といいます。そして、全ての歯にはちゃんと役割があります。
今回は、片噛み癖の意味とそれぞれの歯には役割がありますのでお話していきます。
片噛み癖とは

片嚙み癖とは、食事をする時に、食べ物を口に入れて歯で噛んで食べ物を飲み込むまで左側だけ・右がわだけなどどちらか片側の歯で噛んでいることを「片噛み癖」といいます、噛み方の癖のことを言います。
普段の食事の時に少し意識してみてください。意識にてみると噛みやすい癖があるほうで噛んでいる方が多いのではないでしょうか?
人には、利き手があるように歯にも噛みやすい癖や方向があります。右側だけや左側だけなど、いつも同じ片側だけで食事をしていると、お口の中の健康だけではなく、全身のバランスにも影響が出やすくなります。癖というのは治しにくいものですが、歯と体の健康のためにも治しておく必要がある癖です。
片噛み癖をおこす原因とは

右か左か両方の奥歯の嚙み合わせが悪い
歯の並びが(特に奥歯)悪いことで、左右の奥歯の噛み合わせにも影響がでます。歯の並びが悪いと食べるときにどうしても噛みやすい方の歯(右か左か)で毎回噛んでしまうため意識していないと片嚙みの癖になってしまいます。噛み合わせを治すには歯並びを治療する歯列矯正の治療が必要です。
被せ物がとれたままになっている
虫歯が原因で治療した歯には、銀の被せ物やCRという歯医者さんで使用される白い詰め物をして歯を修復していますが、この被せ物や詰め物が取れたままにしているとその部分に食べかすなどがつまりやすくなるため、その歯を使って食べなくなってしまいます。
例えば右側の歯の被せ物がとれていたら、健康な歯の左側で食べる癖がついてしまいます。片嚙みの癖もですが、虫歯治療をしたあとの被せ物または詰め物が取れたままにしてしまうとそこから虫歯になってしまい、さらに大きく歯を削ることになりますので、早めにかかりつけの歯科医院で治療をしてください。
虫歯を放置している
虫歯があるまま治療をせずに放置していると、歯の痛みや歯がしみたりしてきます。
痛みなどがあると人は無意識にそこを避けようとするため、痛みがない方で噛んでしまいます。初期の虫歯は痛みがないため、「虫歯で歯が痛い」というのは、かなり進行した虫歯になります。この場合も、そのままにせずに歯科医院での治療をするようにしてください。
左右どちらかに知覚過敏がある
冷たい物や熱い物を食べたり飲んだりしたときに歯がしみることがあれば、それは知覚過敏になっています。
歯がしみる事でやはり無意識にしみない方で噛んでしまう癖がついてしまいます。知覚過敏の原因は様々ありますが、知覚過敏だけであれば歯科医院でしみ止めを塗布してもらえば症状は改善します。
何らかの原因で歯が抜けたままになっている
虫歯を放置したままにしていた・重度の歯周病・外傷などで歯が抜けてしまった場合も放置していると、その部分では食べ物を噛めたりできないため噛める反対の歯でばかり噛んでしまうことになります。
歯が抜けてしまっても、今ではインプラント治療も主流になってきていますので、そのままにせずに歯科医院でご相談をしてみてください。
片噛みの癖によっておこる悪影響

癖になっているいつも噛んでいる側の歯がすり減ってしまう
片嚙みの癖があるといつも同じ片方の歯で噛んでいるため、その歯ばかり使いすぎてしまい歯がすり減ってしまいます。すり減る以外にも、歯に負担がかかりすぎてヒビや亀裂がはいることがあります。
いつも噛めていない歯は虫歯になりやすい
反対に噛んでいない方の歯は、食べる時の唾液の量が減ることにより、食べかすがたまりやすくなり、歯垢や歯石がつきやすくなります。歯についた歯垢や歯石は虫歯の一番の原因です。また、虫歯になりやすいことは歯周病にもなりやすくなります。
顎関節症になりやすい
食べ物を噛むことでお口の周りやお顔の筋肉を使います。いつも片側ばかりで噛んでしまう片嚙みの癖がある方は、この食べる時の筋肉のバランスが悪くなってしまうことで、顎関節症になりやすくなります。顎関節症になると、お口を開けづらくなるなど生活に支障がでることがあります。
顔や顎が歪んでしまう
片嚙みの癖が長ければ長いほど、お口の周りの筋肉やお顔の筋肉の使い方が左右非対称になるため、真正面から見たときに左右のお顔のバランスやお口元(顎)が歪んできてしまいます。口角の左右のズレや、ほうれい線の深さや長さ、目元の微妙な高さの違いなど現れることがあります。
左右のバランスが崩れ全身に影響がでる
お顔やお口元が片嚙みの癖で歪んでしまうと、全身のバランスにも影響がでます。例えば片方だけ肩こりがひどい・首の痛みや頭痛などを引き起こされます。全身の筋肉にも影響がでることもあり姿勢や歩き方が悪くなってしまうこともあります。
まとめ

今回は、同じ片側の歯(右たけ・左だけ)でばかり噛んで食べる片嚙みの癖についてお話しました。
食事は日々の生活をする上でとても大切なことですが、つい無意識に片側でずっと食べ物を噛んでいると、毎回の食事をするたびに全身のバランスが崩れることになります。歯やお口の中だけではなく、全身の不調の原因になります。
お口の中と歯と体の健康を考えると片嚙みの癖はぜひ治してほしい癖です。もし、治療が必要な歯があれば歯科医院にいき早めに治療をするようにしましょう。
歯列矯正治療後のあと戻りについて
こんにちは。
神戸市垂水区にある矯正専門歯科医院のふじよし矯正歯科クリニックです。
今回は歯列矯正後に起こる、歯ならびの「あと戻り」についてのコラムになります。
長い治療期間を経て、きれいになった歯ならびが数年後、元に戻ってしまうと残念な気持ちになってしまうかと思います。なぜ、歯列矯正治療後にあと戻りが起こってしまうのでしょうか。その理由や原因などをご紹介します。

歯列矯正後のあと戻りとは?
- 歯列矯正治療後の歯ならびが、歯列矯正前の歯ならびのように崩れてしまうことを「あと戻り」といいます。
歯列矯正治療後、特に矯正装置を外した直後は歯の周囲の骨が安定してないため、歯がとても動きやすい状態となっています。そのままの状態で放置すると、歯は元に戻ろうとします。
後戻りをする原因
歯列矯正治療後にあと戻りをしてしまう原因はいくつかあります。
一般的な原因としては、リテーナー(保定装置)の装着時間が足りていないということが、多くあります。歯列矯正治療後の歯は、先ほどお話したように歯が動きやすい状態のため、リテーナーを装着する必要があります。
また、食いしばりや歯ならびの癖があると歯ならびに影響を及ぼすことがあります。他には、加齢現象による骨の変化や歯周病の進行などもあと戻りの原因となることがあります。

後戻りをしてしまったら...
歯列矯正治療後にあと戻りをした場合、自力で治すことは不可能でしょう。自分の指で歯に圧をかけたりしてしまうことで余計に歯ならびが悪くなってしまったり、歯の寿命が短くなってしまうリスクがあります。
歯列矯正の再治療の方法として、
- ・ダイレクトボンディング法
・ワイヤー矯正法
・マウスピース型矯正法
・ラミネート型矯正法
・セラミッククラウン法
などが挙げられます。
場合によっては、歯と歯の間を削る処置を行うことがあります。
リテーナーの重要性
歯列矯正治療後、リテーナー(保定装置)を適切に装着しなければ、きれいにした歯ならびが崩れる可能性があります。
特に、矯正装置を外した直後から1年ほどは歯が動きやすい時期となります。そのため、この期間にリテーナーを適切に装着しなければなりません。装着しない場合、歯のあと戻りが起こってしまう可能性が高くなります。
当院では、リテーナー(取り外し式)をお渡しした日から1年間は毎日1日中、食事や歯磨きを行う時以外の時間はリテーナーの装着をお願いしています。
リテーナーにも様々な種類がありますが、当院ではほとんどの方に取り外し式のリテーナーを使用していただいています。
数年後に歯ならびが変わる理由
歯列矯正治療を終えてから数年後、歯ならびに少しずつ変化が出てくることがあります。考えられる理由として、いくつかご紹介します。
・加齢現象による骨密度の変化
・食いしばりや歯ぎしりなどによる影響
・生活習慣などによる噛み合わせの変化
・虫歯や歯周病の進行
このような影響を最小限にとどめるためには、定期的に歯科医院に受信することをおすすめします。

まとめ
歯列矯正治療後は、リテーナーを装着する重要性や数年後に歯ならびが変化する可能性があることをお分かりいただけましたか。
これらの原因は、リテーナーの装着時間不足や加齢現象による骨密度の低下が原因となります。
あと戻りを防ぐためには、リテーナーを決められた時間を守って正しく使用しましょう。また、歯ぎしりや食いしばりなどの癖があるという方は一度歯科医院で相談してみることをおすすめします。定期的に歯科医院に行くことで、噛み合わせや虫歯のチェックや歯のクリーニングを行うことで歯ならびの変化が最小限にとどめることが期待できるでしょう。
日本矯正歯科学会学術大会参加のため休診いたします
9月30日(火)10月1日(水)10月3日(金)は、第84回日本矯正歯科学会学術大会参加のため休診いたします。
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
冷たいものが歯にしみる原因と対策について
こんにちは。
神戸市垂水区にある矯正歯科専門医院のふじよし矯正歯科クリニックです。
いつも当院のコラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は、「冷たいものが歯にしみる原因と対策について」お話していこうと思います。
普段の生活で冷たいものを口にした時、しみる・痛みを感じるといった経験をしたことはありませんか。
冷たいものが歯みにしみたり、痛みを感じた症状があるという方は知覚過敏を起こしている可能性が高いと考えられます。暑い季節になると、特に冷たいものを口にする機会が増えると思います。

知覚過敏について
知覚過敏とは、
- ・冷たいものを食べたり飲んだりした時
- ・歯ブラシの毛が歯に触れた時
- ・甘いものを食べた時
- ・歯に風が当たった時
などの場面で、歯に痛みを感じる症状のことを指します。むし歯ではない場合や歯の神経が炎症していない場合でこのような症状を感じる方は知覚過敏になっている可能性があります。
知覚過敏を引き起こす原因について
まず、歯の表面はエナメル質という硬い組織で覆われています。そして、エナメル質の中には象牙質という組織があります。
何らかの原因でエナメル質が薄くなってしまったことで象牙質が露出し、知覚過敏が引き起こされることになります。知覚過敏による痛みは一瞬で治まりますが、冷たいものや甘みにあるものに触れるたび、不快な気持ちを感じてしまいます。
象牙質が露出する原因としては、歯の摩耗や咬耗が挙げられます。歯が摩耗や咬耗をする原因としては、歯ぎしりなどが原因となります。

知覚過敏の原因について
知覚過敏の原因となる理由は主に5つ挙げられます。
歯の咬耗(こうもう)による知覚過敏
普段の生活で歯を使うことで、自然と歯はすり減ります。
噛むことで歯がすり減ることを咬耗といいます。個人差はありますが、歯の咬耗により知覚過敏が起こる可能性があります。また、歯ぎしりを普段からする癖がある方や食いしばりの癖がある方は、歯がすり減ってしまったり、歯にひびが入ってしまうことが考えられます。
歯のすり減りやひびが入ることにより、知覚過敏の症状が出てくる可能性があります。歯に強い力がかかることにより、くさび状欠損(=歯の根元部分が欠けてしまうこと)という症状を引き起こしてしまうリスクがあります。くさび状欠損が起きてしまうと、その部分から知覚過敏が起こることも多くあります。
歯肉退縮による知覚過敏
歯肉退縮とは歯肉が下がってしまうことです。歯肉が下がることにより知覚過敏が起こる可能性は高くなります。
知覚過敏の多くは歯肉が下がったことが原因といえるでしょう。歯肉が下がることで、歯肉に覆われていた歯の根っこが露出してきます。
歯の根っこは、歯の表面にあるエナメル質という硬い組織の部分はありません。なので、エナメル質の中にある象牙質が露出(むき出し)した状態になってしまうことになります。そのため、歯肉が下がることで刺激を感じやすくなってしまいます。
むし歯治療の刺激による知覚過敏
むし歯の治療の時、歯の表面のエナメル質の中の象牙質という部分まで歯を削った場合、どうしても歯に神経に刺激が加わってしまいます。この時の刺激が影響して神経が、過敏になってしまうので、治療の直後は冷たいものがしみやすくなる可能性があります。
ホワイトニングによる知覚過敏
ホワイトニングの薬剤による刺激が原因となり、一過性の知覚過敏が起こる場合があります。施術中や施術後に起こることが多いです。ですが、ほとんどの場合、24時間以内に知覚過敏による痛みは軽減されることが多いです。
酸蝕症(さんしょくしょう)による知覚過敏
酸蝕症とは、酸性の食べ物や飲み物などにより、歯が溶けてしまう病気のことです。
この酸蝕症により溶けてしまった歯のことを酸蝕歯(さんしょくし)と言います。清涼飲料水やお酢、柑橘類といった酸性の飲食物を頻繫に食べたり飲んだりしている場合や長時間お口の中に含んでいる状態が続くと、歯が全体的に溶けてしまいます。
これらの事が原因となり、エナメル質の中の象牙質が露出してしまうことで、知覚過敏の症状を感じることがあります。
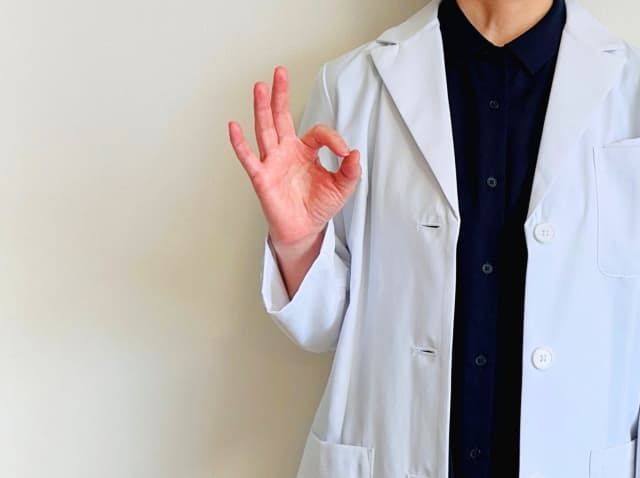
知覚過敏の対処法について
知覚過敏が起きた時の対処法を5つ紹介します。
シミ止めのくすりを塗る
歯科医院で知覚過敏による痛みを軽減するために、薬を塗ることがあります。そうすることで歯の表面に刺激が伝わりにくくなります。この対処法は、比較的軽度な知覚過敏の症状に適しているといえます。
フッ素を塗る
フッ素を歯の表面に塗ることで歯の表面のエナメル質を強化し、知覚過敏による症状を和らげます。フッ素には歯を石灰化させる働きがあるため、歯にフッ素を塗ることで知覚過敏の進行を抑制することが期待できます。歯にフッ素を塗ることを複数回続けることで、効果が持続できます。
知覚過敏用の歯磨き粉を使用する
知覚過敏の症状を感じ始めたら、市販で売っている知覚過敏用の歯磨き粉を使用することをおすすめします。実際に効果を感じられたという患者さまも多数おられます。また、フッ素濃度が高いものを使用すると更に良いでしょう。知覚過敏用の歯磨き粉を持続的に使用することで、効果が期待できます。
レジン(歯科用のプラスチックの材料)を使用する
歯ぎしりなどが原因で歯と歯肉の境目がくさび状になっていることをくさび状欠損と言います。くさび状欠損は知覚過敏の原因となる可能性があります。このような場合、歯科用のプラスチック材料を詰めることで症状を軽減することが期待できます。
マウスピースを使用する
歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、歯のダメージを防ぐためにマウスピースを着用することがあります。特に夜間の装着を勧められる場合が多いです。
神経を抜く
知覚過敏の症状がひどい場合、他の治療方法では改善が見られない場合や日常生活に支障が出てしまう場合は、最終的に神経を抜く治療を行うこともまれにあります。神経を抜くことで、知覚過敏の症状は治まりますが、歯の感覚も失ってしまうため慎重に歯科医師と話し合い、相談する必要があるでしょう。
まとめ
知覚過敏の症状や原因、知覚過敏になった場合の対処法についてお分かりいただけましたか。
もし、知覚過敏の症状が長引いている場合や痛みが強くなってきていると感じたら、一度歯科医院を受診することをおすすめします。
歯とはちみつ!歯に良いのか?悪いのか?

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
今回は、歯とはちみつは歯に良いのか?悪いのか?についてお話していきます。
皆さん、はちみつを普段どれくらい口にしていますか?去年ぐらいからアサイーやグリークヨーグルトが流行し、自宅で作っている方もおりますし、街中でも人が並んでいる光景を見かけたかたが多いと思います。
どちらも上に新鮮なフルーツやグラノーラがのっており最後にはちみつがかかっています。他にも、パンやホットケーキ・料理にもはちみつを使うこともありますし、風邪などで喉が痛いときは暖かい飲み物にはちみつを溶かして飲むことで痛みがやわらぐこともあります。
また、かなり余談ではありますが、私は最近はちみつがマイブームです!はちみつ専門店に行くとワクワクします。自宅には4種類のはちみつを常備しております。
実は、はちみつはあんなに甘いのに虫歯になりにくいのです。もちろん毎日大量に摂取するのは歯だけではなく体にも良くはないのですが、少量であればお口に中はもちろん、体にもさらには美容にも良いのがはちみつの効果でもある抗菌作用です。
そもそも虫歯になる原因とは

皆さんは虫歯になる原因をご存じでしょうか?お菓子やジュースなどの間食が多いからと思うかもしれませんが、間違いではないのですが、実際にはお菓子やジュースの糖分が虫歯になる原因ではなく、虫歯になる菌(ミュータンス菌などの細菌)を作りだしてしまい虫歯になるのは、糖ではなく酸なのです。
歯磨きが不十分で歯に歯垢(プラーク)や食べかすがついていると、虫歯菌(ミュータンス菌などの細菌)が歯に残っている、食べかすなどの糖を分解しようとして酸を発生させます。この発生した酸が歯を溶かしてしまい虫歯になります。
糖は特に砂糖(ショ糖)に多く含まれているので、間食が多くお菓子や甘いジュースを口にすることが多いと、糖を分解するために酸が多く発生してしまい虫歯になるリスクが高くなります。
虫歯予防のためにも間食したあとにも歯磨きを忘れないようにしましょう。
はちみつが体になぜいいのか?

はちみつを食べると甘いのは皆さんご存じだと思いますが、実ははちみつには甘いだけではなくて体にとっても良く健康になるためのとても大切な成分が多く含まれています。
はちみつにはビタミンのB群やビタミンCが多く含まれています。ビタミンの他にもカルシウムやカリウム、鉄や亜鉛などのミネラルも多く含まれており、ビタミンはお肌や体の健康の維持や免疫力があがりますし、カルシウムやカリウムなどのミネラル成分は、骨や筋肉を強化してくれます。
他にも、酵素やアミノ酸、ポリフェノールやグルコン酸など沢山の栄養がバランスよく含まれています。これらの栄養素は、腸内環境を整え、風邪をひいた時の咳や喉の痛みを和らげる効果もあります。美容や健康の維持や改善にとても優秀な食べ物です。
砂糖とはちみつの違い

同じように甘い物の代表は、砂糖だと思います。皆さんは砂糖とはちみつの違いがあるのをご存じでしょうか?
そもそもですが、砂糖とはちみつでは甘味の成分が全く違うのです。はちみつの甘さは砂糖と違い、はちみつの主な成分は果糖とブドウ糖からできています。
一方で砂糖の主な成分はショ糖からできています。ショ糖は、歯につきやすく残りやすいため虫歯になる虫歯菌を発生しやすくなり、この虫歯菌がショ糖を分解しようとすると酸がお口の中に広がり、酸が歯を溶かしていき虫歯になりやすい状況を作ってしまいます。なので、砂糖を含む食品や飲料水(ジュースなど)を頻繁に摂取していると虫歯になりやすくなります。
砂糖が含まれている食べ物や飲料水など甘い物を食べた後はもちろんですが、砂糖は料理にも使われていますので食事の後は歯磨きをするのが虫歯の予防になります。
はちみつの主な成分の果糖とブドウ糖は、お口の中で溶けやすく歯への付着も少ないため虫歯にはなりにくいですが、全ての「はちみつ」とは言えませんので、注意が必要です。
はちみつの種類によっては虫歯になる

これまで、はちみつは虫歯になりにくいとお話してきましたが、全てのはちみつではないので注意が必要です。
はちみつには種類が多く、それぞれに違いがあります。スーパーマーケットなどに置いてあるはちみつは「アカシア」「れんげ」など一般的によく見かけるのではないでしょうか?
はちみつは大きく分けると「単花蜜」と「百花蜜」の二種類になります。この二種類の違いは、ミツバチの種類も違うのです。単花蜜は、セイヨウミツバチが一つの花の蜜を採取して蜜箱に集めたものをいい、百花蜜は、ニホンミツバチが沢山の花の蜜を採取して蜜箱に集めたものです。
このニホンミツバチの数がかなり少なくなってきていて、百花蜜は高価なはちみつになっています。他にも、はちみつには加工の方法によって「純粋はちみつ」・「加糖はちみつ」・「精製はちみつ」の三種類があり、歯と健康のために選ぶのであれば、必ず「純粋はちみつ」と明記されたものを選んでください。なおかつ養蜂場の名前などが記載されていると、加工などされていない、本来のはちみつを選べると思います。
余談ですが、ニホンミツバチの数が少ないと話ましたが、はちみつ専門店に行くと小さな瓶で三千円ぐらいします・・・。本当にお高いのですが、味と香りが濃厚で普通のはちみつとの違いがすごくわかります。
まとめ
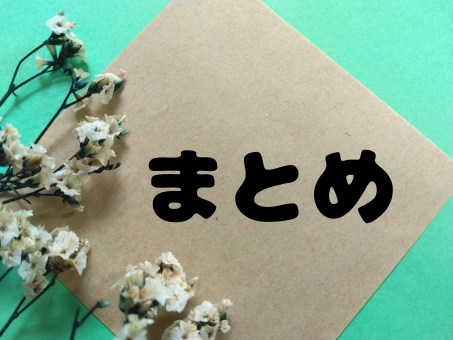
今回は、私自身が最近はまっている「はちみつ」についてと、はちみつは実は歯にも良いことが分かったのでコラムの記事にしてみました。
このコラムを書くにあたって色んな記事を読みましたが、中には「はちみつをつけて歯磨き」とか、「寝る前にはちみつを食べて寝る」とか色々とありましたが、はちみつで歯磨き・・・。さすがに実験できていないです。
寝る前にはちみつは、高齢者の方とか、唾液量が極端に少ない方には良いのかも?と思いました。毎日摂取するにはかなり高価なはちみつですが、お口の中や美容も含めて、これからの健康維持の一つとしてお試しください。
美容と健康に良いはちみつですが、1才未満の乳幼児には与えないようにご注意ください。
銀色のワイヤーと白色のワイヤーの違いについて

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。
いつもコラムを読んでいただきありがとうございます。
今回は、歯並びを治療する矯正歯科で行うワイヤーでの治療で使用する、標準の銀色のワイヤーと白いワイヤーの、それぞれの特性と違いやメリットデメリットについてお話していきます。
ご自身の歯並びや、お子様(中高生以上)の歯並びが気になっている方はぜひ参考にしていただければと思います。
当院では、標準の銀色のワイヤーはもちろんですが、オプションで別途料金が必要ですが、ご希望があれば白いワイヤーを選択できます。
詳しい料金は当院のホームページをご覧ください。
歯並びを治療するワイヤー矯正とは

「矯正」と聞けば、まずワイヤーが歯についているイメージが最初に思うのではないでしょうか?ワイヤーは、中高生以上で永久歯が生えそろっている方の矯正治療で使われています。
歯の表面に一個ずつブラケットというワイヤーを固定する装置をつけ、ブラケットの溝にワイヤーを通していきます。
歯の表面につけたブラケットにワイヤーを通すことで、歯に動かす力を加えることができ、少しずつ歯が動いて歯並びを治していきます。
普段見えている歯の下(歯茎の中)には、歯槽骨という骨があります。
この歯槽骨と歯の間には柔らかいクッション性のある歯根膜があります。
歯に動かす力がかかると、この歯根膜は刺激され縮みます。
縮むと元に戻ろうとするときに動いていく方向の骨を溶かしていき歯は動いていきます。このことを吸収といいます。
歯が動いていく方向の歯の反対側は、歯根膜が引かれることによって伸びます。
伸びて薄くなると元の厚さになろうとして骨を作ろうとします。このことを再生といいます。
歯並びを治す矯正治療は、この吸収と再生を繰り返して治療をしていきます。
銀色のワイヤーと白色(ホワイト)ワイヤーの違い


矯正治療といえば、銀色のワイヤーやブラケットが歯についていて銀色の装置がギラギラと目立つイメージではないでしょうか?
当院でも、標準のワイヤーは銀色になります。が、目立つのはワイヤーを固定している歯の表面につけるブラケットが銀色の場合です。
当院では、笑ったり会話した時に歯が見える部分は透明のブラケットを使用しております。
奥歯は銀色のバンドという装置になりますが、奥歯なので目立ちにくいように配慮しております。
同じ人が銀色のワイヤーと白色のワイヤーとつけたものが上記の写真です。
一番最初のワイヤーなので細く柔らかいワイヤーなので皆さんが思っているよりも違いはないように見えるかもしれません。
ただ、ワイヤーは歯並びを治していく矯正治療の間、歯の動きによってだんだんと太く硬くなっていきます。
最初から治療が終わる最後までずっと写真のような細さのワイヤーではないので、ワイヤー治療をする場合は、標準の銀色のワイヤーにするのか・より目立ちにくい白いワイヤーにするのか治療の前に決めていただく必要があります。
白いワイヤーよりも目立ちにくのは、マウスピース治療になりますが、マウスピース治療は全ての患者様に適用するのが難しく、マウスピース治療で矯正治療ができるか判断するのは歯科医師になります。
標準の銀色のワイヤーのメリットデメリット

銀色のワイヤーの一番のデメリットは、「ワイヤーが銀色のため歯と色が違ってしまいワイヤーが目立つ」だと思います。
昔(数十年前)は、ブラケットもワイヤーも銀色が主流だったのでそのイメージが強いかもしれませんが、今は、各メーカーから目立たない透明のブラケットも多数出ており、当院でもワイヤー治療のかたは皆さんに透明の目立たないブラケットを使用しております。
それでも、ワイヤーの色は銀色だと他の人から見た時にワイヤーが目立ってしまいます。
少し前ですがコロナ過のとき、一斉に子供も大人も皆がマスク生活になり人前で歯を見せることがなくなったとき、実は歯並びを治すために矯正治療をするかたが増えていました。
その時に、銀色のワイヤーにするか白のワイヤーにするか悩んだ方は少なかったのです。何故なら、「マスクをしているから」です。
通勤通学時も会社内や学校内、遊びに出かけるときも皆さんマスクをしていたので、別途料金がかかる白いワイヤーを選択されるかたが少なかったです。
やはり、矯正治療はしたいけど、人から見たときに知られたくない。という気持ちがあるのかと思います。
次に銀色のワイヤーのメリットですが、やはり長年の治療結果があり、歯の並びが軽度であっても重度であっても治療が可能なことです。
歯の並びが比較的重度な場合、マウスピースで治療することが困難な場合もありますが、ワイヤー治療だと治療可能になることです。
ちなみに、ワイヤーの色が銀色でも白でも矯正治療にかかる治療期間は同じになります。
白いワイヤーのメリットデメリット

白いワイヤーを選ぶ一番の理由は、「目立ちにくい」だと思います。
やはり白いワイヤーのメリットは、歯とワイヤーの色が近いため他の人から見て銀色のワイヤーよりも矯正治療をしていることが気づかれにくいと思います。
ただ、白いワイヤーは銀色のワイヤーを白くコーティングすることで白いワイヤーになっているため、食事や歯磨きなどでこの白いコーティングがとれてしまうと下の銀色が見えてきてしまうことがあります。
コーティングが取れてしまうと銀色が出てきてしまうのがデメリットかと思います。
ワイヤー治療の方が来院された場合、毎回ワイヤーの調整をしますが、調整の内容によっては、元のワイヤーを戻す場合と新しく次のサイズのワイヤーに変える場合とあります。
新しいサイズのワイヤーに変える場合は白いですが、そのままのサイズのワイヤーを戻す場合は、食事や飲食などで少し黄ばむこともあり真っ白ではないこともあり、さらにコーティングもはがれやすいため、白さが損なわれることもあります。
白いワイヤーを選ぶ際には、着色で黄ばむこともある・白いコーティングがはがれてしまいワイヤーの一部が銀色になってしまうこともあることを理解した上でワイヤー治療の選択をしていただければと思います。
まとめ

今回は、歯の並びを治療するうえで一番主流のワイヤー治療でのワイヤーの色の違いについてお話してきました。
中高生以上の方が矯正治療だとまずワイヤーを用いたワイヤー矯正になりますが、ワイヤーには標準の銀色のワイヤーと白いワイヤーがあること、それぞれのメリットデメリットがあること、白いワイヤーは別途料金が必要なことを考慮して数年かかる矯正治療をお考えいただければと思います。
当院では、歯並びを治すための相談は初回無料でございます。気になる方はお気軽にご連絡をお待ちしております。